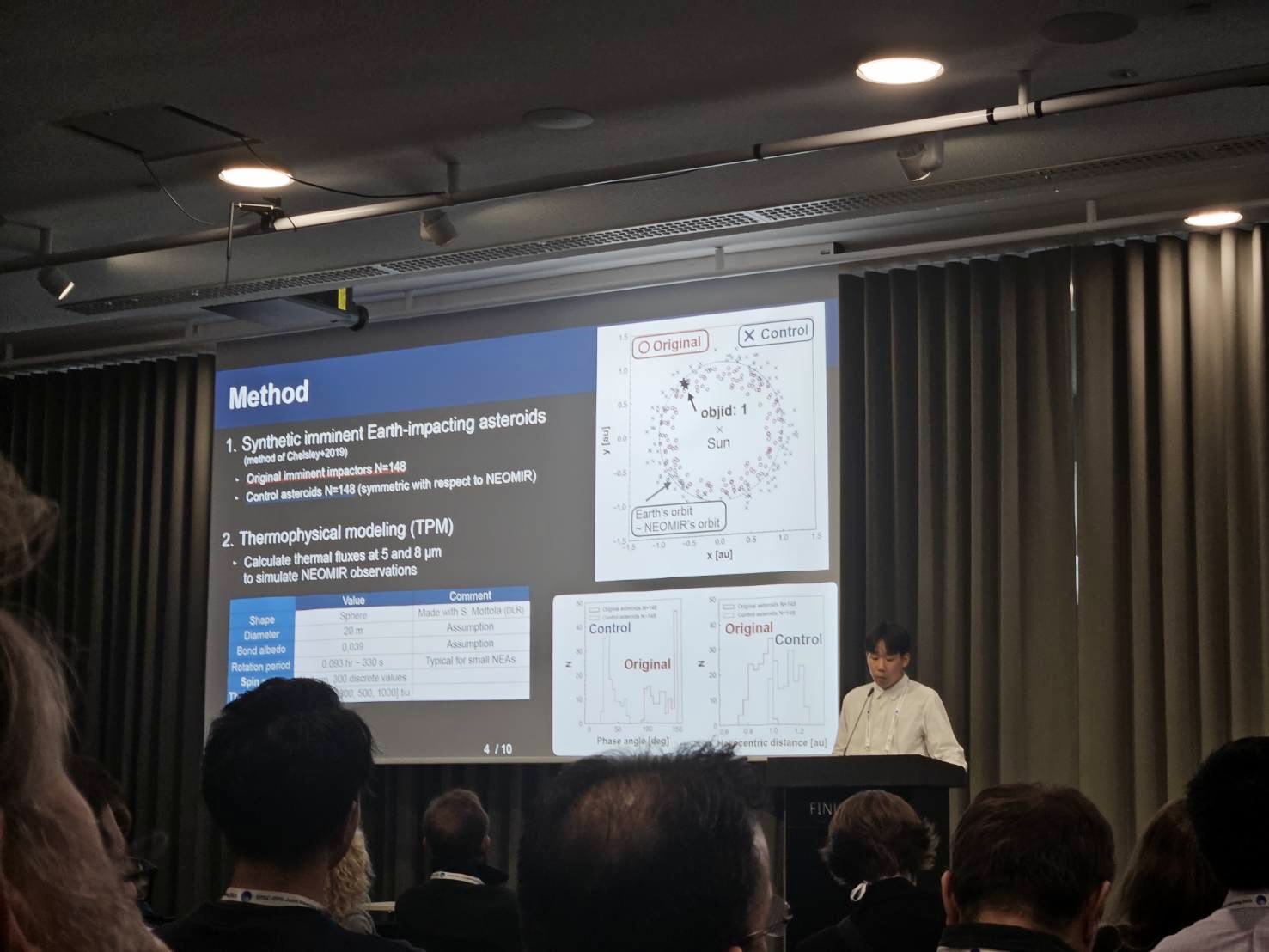
2025年10月7日 紅山 仁 (コートダジュール天文台)
2025年9月、フィンランドで開催された国際研究会 Europlanet Science Congress (EPSC) に参加した。EPSC は欧州の惑星科学コミュミニティにおける主要な会合の一つだ。主に欧州内から1000人以上が参加する、いわゆるマンモス研究会だ。昨年度は渡仏後の滞在許可証取得に手間取り、現地参加を断念した因縁のある研究会でもある (昨年参加できなかった詳細は月刊コートダジュール2024年11月号を参照)。今年は米国天文学会の会合 Division for Planetary Sciences (DPS) Meeting との共同開催ということもあり、参加者は合計1803人に達した。
研究会の雰囲気は重要だ。議論の時間が十分に確保されているか、そして活発な議論を促すためのスペースや飲食物の有無なども、重要な要素だと思う。EPSC、DPS ともに現地参加した経験がないため、研究会の雰囲気が掴めずにいたが、参加してすぐに豪華な研究会であることがわかった。おかげでさまざまな共同研究の議論が進んだことは大きな成果であった。しかし、一方で懸念もある。幸い今年度は研究会参加に必要な予算があったが、参加登録料が550 ? (当時のレートで約10万円) と非常に高い。この高額な参加費を理由に現地参加を断念せざるを得ない研究者が少なくないのではないかと懸念する。豪華絢爛な傾向にあるマンモス研究会は、もう少し控えめでも十分価値があるのではないかと毎回感じる。
筆者は ESA (European Space Agency、欧州宇宙機関) の将来計画である宇宙望遠鏡 NEOMIR (NEO Mission in the InfraRed)を用いた地球接近小惑星観測について発表した。近い将来、NASA の NEO Surveyor や ESA の NEOMIR といった宇宙望遠鏡が、中間赤外線による観測で多数の地球接近小惑星を発見することが期待されている。とりわけ、太陽方向に近いためにこれまで観測が難しかった小惑星の発見が期待されているが、そのような太陽位相角が大きい観測において、観測結果の解釈方法は確立されていない。コートダジュール天文台の受入教員であるマルコとともに熱物理モデリングの手法を用い、“従来の手法ではどの程度誤った見積もりをしてしまうか” を評価し、その結果を発表した。欧州に拠点を移したばかりの筆者が ESA の将来計画に関わることができているのは、その地の利を生かせているからに違いない。国内外の研究者との活発な議論を通じて、自身の研究に対する重要なフィードバックが得られ、研究を大きく進展させることができた。
研究会といえばその前後 (今回は朝の開始が早かったため主に後) に開催地の文化を楽しむことが重要だ。フィンランド観光の二大看板であろうサウナとムーミンのうち、サウナは存分に楽しめた。「サウナ兄さん」とあだ名されるほど夢中になるわけにはいかないと思いつつも、バルト海に面したサウナを満喫できたのは幸いだった。バルト海は前評判通り透き通ってはいなかったが、冷たさが身体を引き締め、フィンランドの文化を体験することができた。本場のサウナから眺める月がひときわ美しかった
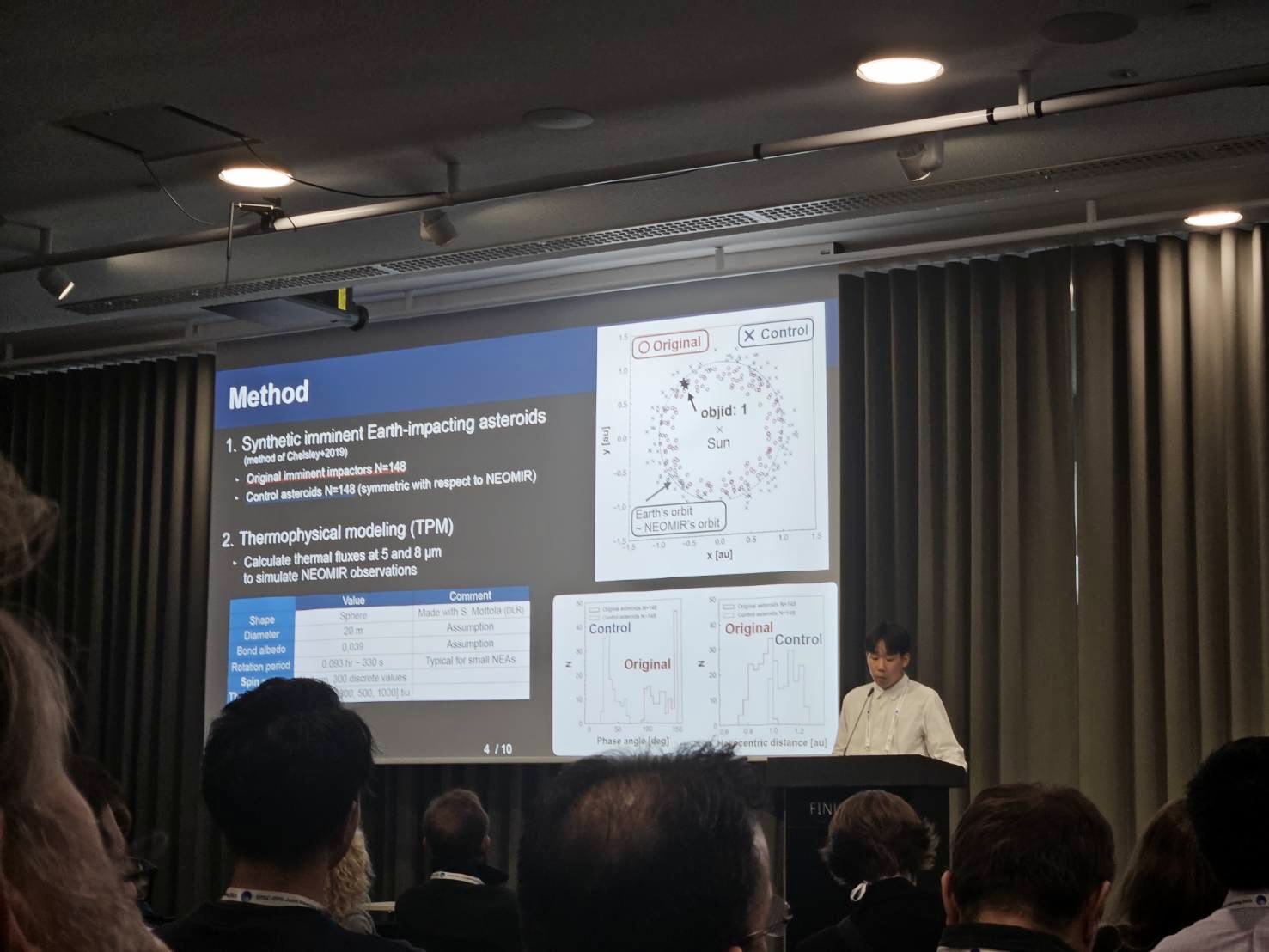
写真1. EPSC で発表する筆者。5日間の研究会のうち最終日の午後に割り当てられた発表であったが、自身の研究成果をコミュニティに向けて発信することができた。
P>
写真2. フィンランドのサウナから眺めた月。ちなみにこの写真を撮影した前日は皆既月食であったが、サーモンスープに夢中で見逃してしまった。